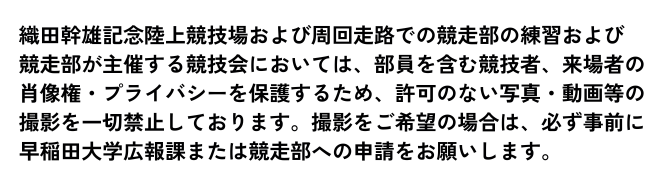最新ブログ
シンガポール遠征通信①

こんにちは。
早稲田大学競走部男子短距離コーチの田村です。
3月10日から3月22日のスケジュールで、短距離ブロックは選抜メンバーによるシンガポール遠征を行っております。現地ではトレーニングに加え、競技会にも参加しております。
本遠征は公益財団法人G-7奨学財団様のサポートのもと実現いたしました。また、遠征実施にあたり多くの関係者の皆さまにお力添え頂いております。この場をお借りして深く感謝申し上げます。
こちらの様子を指導者目線で簡単にお届けいたします。
今回の遠征の目的は大きく分けて2つです。
本日はそのうちの1つについて書きます。
今回の遠征の大きな目的は、シーズンに向けた温暖地での調整と競技会参加による競技力の向上です。その中でも国際競技力という視点から書きたいと思います。
海外での競技会参加、特にローカルな試合の場合は急な競技日程の変更やスタートリストへの記載漏れなど小さなトラブルが頻発します。今回、シンガポールで参加する競技会も例にもれず、小さなトラブルに学生が巻き込まれています。
もちろん、競技に関わる者としてはこの手のトラブルは非常に厄介ではあるものの、同時に日本で運営されている競技会のレベルの高さに改めて感謝をしなければと感じます。ほとんどミスなく、タイムテーブル通りに進行される競技会はとても恵まれた環境であると再確認させられます。
一方、アスリート目線で考えると、レベルにもよりますが、どんな状況下でも走ることのできる「タフさ」が求められます。「タフさ」については監督の大前がユニバーシアード観戦記でも記していましたが、実際にその現場に立つと強く実感できます。
「急遽日程が変わったから」、「追加でこの種目も出られるようになったけど、ちょっと…」。
よく聞く言葉ですが、慣れない環境下で挑戦できる機会があるからにはそれを積極的につかみに行く、それを掴むだけの体力・気力が求められるのではないかと感じます。また、そのような体力・気力を高めていくには、普段からどのような取り組みが求められるのか。
もちろん記録や順位を残すことは重要です。しかし、海外でそのような成果を残すには、その前提として臨機応変な順応力とタフさが重要になると感じます。
グローバルなアスリートを目指すうえでは欠いてはならない視点です。
また、今回の遠征に参加しているメンバーは実際にこのことを肌で感じていると思いますから、そのことを帰国後どれだけチームに還元できるか。この点に期待したいです。
こちらの原稿を書いている本日(現地時間3月15日夜)は競技会の初日でした。
競走部からは1年内藤が走幅跳に出場しました。結果は記録だけ見れば満足のいくものではありませんが、それ以外の収穫が大きかったのではないでしょうか。
慣れない環境下の試合でしたが、大きなトラブルもなく、しっかりとピットに立ち、記録を残すことができました。当たり前のことですが、初めての海外での試合であった彼女にはきっと大きな経験になったと思います。
彼女の試合を見ていて、良かったなぁと思ったことがあります。
一緒に遠征に来ていたメンバーが、いわゆる「集団応援」をして彼女を盛り上げていました。シンガポールにその様な文化はありませんから、会場の人たちが「なんだ!?」と驚きます。
一緒に観戦していたシンガポールのコーチには「これが日本での応援の仕方なんだ。みんなで一つになって選手を応援するんだ」と説明しました。コーチは「それはすごく良い!しかも海外でやるなんて勇気の必要なことだし、現地の選手も刺激になるよ!」と。他の指導者からも「日本は一体感があっていいね!」、「早稲田の応援は素敵だ!」とお声がけ頂きました。
文化は違えど、一体感を感じる空気感は万国共通。こういった側面でいわゆる「日本らしさ」、「早稲田らしさ」を表現できたことはチームとしても一つの収穫だったのではないでしょうか。
明日以降(3月16日以降)、競技会が本格的にスタートします。
どんな結果が出るかはもちろんですが、学生がどんな表情、雰囲気で競技会に臨むかを楽しみにしたいと思います。